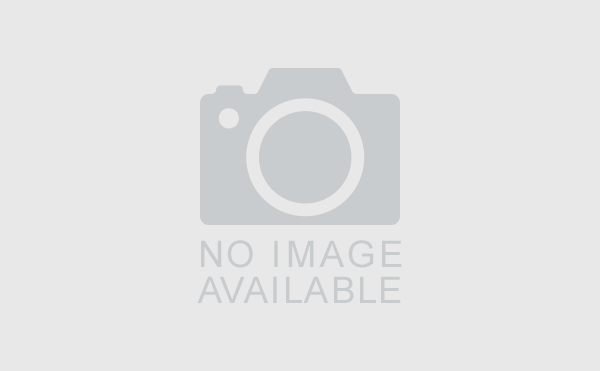教会ホームページの活性化のための10の提案
1.教会が活性化すればするほど、教会ホームページも活性化する。そうでない場合、つまり教会ホームページは活性化しているが、教会は沈滞しているという羊頭狗肉なケースも「あり」。教会ホームページが教会を活性化することもありうる。
2.教会の建物や設備よりも、そこにどれだけ「信仰の喜び」が表現されているか、それを読み取れるホームページでありたい。
3.教会ホームページは、教会メンバーを対象とするのではなく、キリスト教を知りたいという人、教会を知りたい、行ってみたいという人の「目線」で表現され、そのニーズに親切に応えるものでありたい。
4.その教会ホームページの、ほかにはどこにも書かれていない個性的でユニークなコンテンツこそが《たから》である。どこにでも書かれているようなことは書かれているどこかとリンクをはればいい。
5.教会の信徒の《いきざまと信仰》があふれ出ている、この教会に行ってこの人と会ってみたいと思わせるような内容をあふれさせよう。
6.教会と地域との関係を表した記事も貴重な《福音=good news》である。町おこしや地域行事への参加、地域で活躍している人の紹介など。その地域を知るために調べているうちに教会ホームページに迷い込んでしまったというケースが生じるのが理想的である。
7.たとえば、キリスト教や信仰についての質問が投稿されるとする。それに神父さんだけが応えるのではなく、いろいろな人があれこれと異なった答えをできるシステムがあったらいい。
8.教会で行われている「入門講座」と連動しているホームページでありたい。
9.他の教会ホームページで行われていること、かかれていることを自分の教会でもやってみて、リンクを張る。他の教会のコンテンツもあたかも自分の所のもののように取り込むというのがかしこいやりかたである。
10。教会ホームページに笑顔の写真を溢れさせよう。人の顔をぼかしたり、顔のない写真をアップするのは《愚の骨頂》である。プライバシー恐るるに足らず。
11.ホームページに掲載する記事を主任司祭の事前検閲制ではなく、アップしたらそれをチェックするというし事後報告制にする。
12.その教会の独自なテーマがあったらいい。たとえば「家族」たとえば「教会と音楽」たとえば「祈り」。そのことを知りたいならそのホームページにいけばいいというふうになったらいい。リンク集だけでもいい。たとえば「キリシタンを主人公とする小説リンク集」みたいなもの。